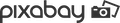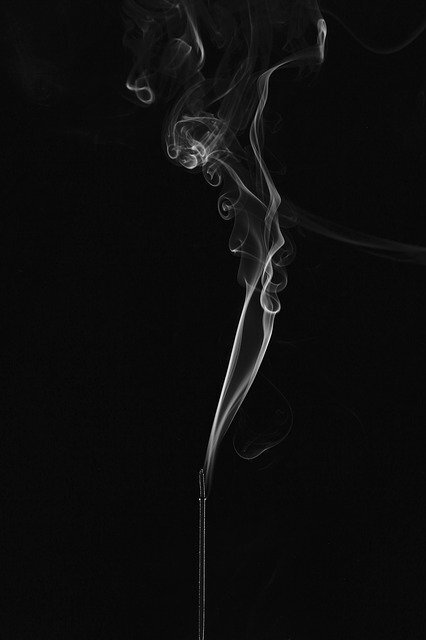本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。
日本人なら一度は見ておきたい国宝「奈良の大仏」
「奈良の大仏」は、言わずと知れた観光名所であり、関西へ修学旅行に行った人で東大寺がコースに含まれていた、という人も多いため、日本人の多くが見たことのある大仏です。奈良の数ある国宝のうちの1つで、奈良時代に制作された後、修理などを重ねて現在に残っています。
とてつもなく大きい仏像、というだけでも一見の価値があるのが奈良の大仏ですが、東大寺大仏殿やその成り立ち、仏像の作りや意味といった秘密を知れば、大仏の鑑賞も人一倍楽しめます。
東大寺 大仏殿(金堂)へのアクセス
奈良の大仏があるのは、奈良県奈良市にある華厳宗のお寺「東大寺」の中の大仏殿です。境内の中でも南大門からまっすぐ北に行った奥にある建物、大仏殿に大仏が配置されています。大仏殿は「金堂(こんどう)」とも呼ばれています。
お寺における「金堂」とは、お寺の本尊を祀っているお堂のことなので、大仏は東大寺の中心とも言える部分です。そのため東大寺に入ってから大仏殿までは少し距離があります。
まず、東大寺へ行くためのアクセス方法としては公共交通機関によるアクセスをメインとする方法、そして自家用車などで向かう方法が挙げられます。公共交通機関を用いたアクセス方法は近鉄の奈良駅から徒歩、または駅から出るバスに乗って行く行き方です。
東大寺へアクセス可能なバスは、JRの奈良駅及び近鉄の奈良駅から出ている「市内循環バス」と、近鉄の奈良駅から出ている「ぐるっとバス」です。バスでのアクセスなら、市内循環バスでの最寄りバス停が「東大寺大仏殿・春日大社前」、ぐるっとバスでは「大仏殿前駐車場」となっています。
また、車でのアクセスであれば、周辺にいくつかコインパーキングがあるので、コインパーキングに駐車すれば行きやすいです。東大寺の西大門側には「GSパーク東大寺西大門駐車場」という有料駐車場があります。
また、春や秋の観光シーズンであれば土日祝日に開いている観光無料駐車場もあるので、訪れる時期に合わせてアクセス方法は前もって調べておくと、現地でのアクセスが便利です。
また、観光用の大型バスなどで訪れる際は大仏殿に最も近い県営駐車場に駐車して向かうというアクセス方法になりますが、県営駐車場からであれば参道が整備されているので車椅子やベビーカーを利用する人のアクセスも楽です。
個人旅行か団体旅行かでも東大寺大仏殿へのアクセス方法は変わるので、自分が観光に訪れる際はアクセスのしやすさも考慮して行き方を決めると良いでしょう。
| 住所 | 奈良県奈良市雑司町406-1 |
| 電話番号 | 0742-22-5511 |
奈良の大仏って?
一般的に「奈良の大仏」と言われる東大寺の大仏ですが、どう作られた仏像なのか、他のお寺の仏像と比べてどう違うのか、あまり詳しく知られていないことも多いです。そもそも奈良の大仏とはどんな大仏なのか、歴史的背景や制作過程などをご紹介していきます。
正式名は「東大寺盧舎那仏像」
奈良の大仏、という俗称が有名ではありますが、正式な名前は「東大寺盧舎那仏像」とつけられています。仏像にはモデルとなった仏の種類によって様々な名前がついていますが、「盧舎那仏」は東大寺の宗派である華厳宗でも中心的な存在として扱われている仏です。
盧遮那仏像の特徴として、蓮華台座や光背(背景の光を表す付属物)にたくさんの仏が描かれていること、仏像本体の装飾などは比較的シンプルであること、手元は右手が手の平を前に見せるような形、左手が「与願印」という印を結んだ独特の形であるといったものがあります。
大仏そのものの詳しい秘密については後ほど述べますが、どういった点が盧舎那仏像ならではなのか、知っておくと実際に見ても発見が多く出来て楽しめます。
745年に聖武天皇の発願で制作
奈良の大仏が制作されたのは西暦745年で、日本史でも有名な聖武天皇の発願によって作られました。費用も手間もかかる大きな仏像をわざわざ作ろうとしたのには、当時の社会情勢という理由があります。
聖武天皇は在位期間が25年とそれほど短くはありませんが、聖武天皇の治世である天平頃は様々な社会不安の多い時期でした。自然災害や疫病の流行と人の力では防ぎ様のない事態が多く発生し、政変や反乱も起こっていました。
人の力ではどうしようもないことが次々と起こる中で、聖武天皇は仏教の力によって社会不安を解消する動きに乗り出します。まずは全国各地に国分寺を建てるようにして、国中に仏教の力が行き渡るようにと考えました。東大寺において盧舎那仏像を制作させたのも、政策の一環です。
盧遮那仏は広大な仏教世界の中心に位置する仏で、太陽のように世界を照らすものとされています。強大な盧遮那仏を大仏として制作することで、当時奈良にあった都を中心に、良い世の中にしたいという願いから、奈良の大仏は作られました。
奈良の大仏のモデルは中国奉先寺の「盧遮那仏」
奈良の大仏が作られた当時、東大寺のものと並ぶほど大きな仏像はなかなか作れるものではなく、奈良の大仏も中国のものをモデルにしたと言われています。中国の都であった洛陽にある奉先寺には、岩の壁から彫り抜いた「大廬舎那仏」があり、現在も観光客が多く訪れる場所です。
中国の奉先寺にある大廬舎那仏は凛々しい顔立ちという印象で、高さ17.14mの大きさです。対して東大寺の盧舎那仏像は顔立ちにおいては柔らかい印象を持たれることがあります。また高さが14.7mなので中国のものと匹敵しながらも少し小さめです。
高さ約14.7メートル基壇の周囲70メートル
先程簡単にお伝えしたように、奈良の大仏は高さが14.7mあり、かつ基壇と呼ばれる仏像が乗っている壇の部分は周囲が70mと、驚くほどの大きさで作られています。見上げると圧倒的な存在感のある大仏の様子は、非常に手をかけて作られたということがよく分かります。
大仏の造形についてちょっとした秘密ですが、地上から人々に見上げられることを前提とした大きさの仏像であるため、奈良の大仏は下から見た角度で良く見えるように顔立ちやバランスを意識して作られたとも言われています。
のべ260万人が工事に関わった
見上げる大きさの大仏を制作するには、相当な労力が必要となります。さらには現代と違って機械なども無くすべて人力で行わなくてはならない大仏建立には、膨大な人数が関与したとされています。
奈良の大仏を制作する過程を簡単に説明すると、まず支柱を組んで原型となる芯を作り、その後完成形を目指して上から土で造形し、中型像を作ります。そして仮の中型を元にして外型を作成し、多少削った中型と出来上がった外型の間に銅を流し込んで鋳造することで出来上がります。
人力で上記のような大掛かりなことをやるため単純に人手が必要となったこと、また作業中の事故や銅を鋳造する過程で発生した水銀中毒で多くの人が亡くなったこともあり、工事には総勢で約260万人もの人が関わったと言われています。
現在の価格で約4700億円
多くの人が工事に関わった奈良の大仏は、制作費用も並外れたものでした。原材料となる銅は約500tもの量が使われたというだけでも、相当な原材料費がかかったことが伺えます。
さらに、大掛かりかつ繊細な作業を必要とする各工程や仏像本体以外の部分の作成、仏像表面に施すメッキも考慮すると、現代の技術であってもかなりの費用がかかる大事業と言えます。奈良の大仏の制作費用を現代の通貨になおすと、約4700億円とされています。
多大の費用と人手をかけるほど、聖武天皇が東大寺の大仏、ひいては仏教の力にかける期待が強かったことが分かります。
1958年に国宝に指定
奈良時代に世の中を良くして欲しいという期待と願いを込めて作られた大仏は、国としても重要なものであるとして、1958年、国宝に指定されました。国宝といってもいくつかのジャンルに分かれており、まず建造物と美術工芸品の2つに大きく分けられます。
美術工芸品の中でも「絵画」「彫刻」「古文書」など7種類の分類があり、奈良の大仏は「銅造盧舎那仏坐像」という名前で、彫刻の部門の国宝とされています。彫刻部門の国宝は木製の像が多いですが、奈良の大仏は銅製のため少数派です。
国宝に指定されてから、奈良の大仏はさらに有名な仏像となり、全国各地から絶えず観光客が訪れ鑑賞されるようになりました。
奈良の大仏の歴史
仏教の力を信じ、費用や時間をかけて作られた奈良の大仏ですが、制作されて終わりではなく、完成後も様々な出来事がありました。大仏は現在に至るまでの歴史において、多くの人の手を借りながら残っています。ここからは、奈良の大仏の現在までの歴史についてご説明します。
752年に「大仏開眼供養会」が行われた
745年に造立が命じられた奈良の大仏は、その7年後の752年に「開眼供養」という儀式が行われました。開眼供養とは、仏像の目に筆で瞳を描き、仏像の中に魂を迎え入れるというもので、通常は仏像がすべて完成した後に行われます。
開眼供養を行った当初、大仏そのものは継ぎ目の接合やはみ出した部分を削るなどの「仕上げ」作業が完了しておらず、正確には未完成の状態でしたが、仏教伝来から200年の節目に合わせて行いたいという要望から、752年に開眼供養が行われたとされています。
当時の東アジアの中では最大級の国際イベント
仏像の完成の儀式と聞くと静かに行われるイメージを持ってしまいますが、奈良の大仏の開眼供養は静かどころか、豪勢に執り行われた一大イベントでした。天皇や皇后が要人として参列した他にも、上位の僧侶の参加が1000人以上、参列者は計1万数千人に及びました。
参列者は僧侶や仏教関係者だけでなく、歌や舞を披露するための人員が招待されました。また国外からも中国・朝鮮からの参列者も多く、海外との行き来すら困難であった時代において、東アジア内では最大級のイベントであったとされています。
儀式での飾り付けも五色の幡や宝樹が飾られ、見た目も音楽も鮮やかで国際色豊かな儀式であったことが想像出来ます。
その後2度の焼失と再興
完成を華々しく祝われた奈良の大仏ですが、ずっと平和に残ってきたわけではありません。まず完成から数十年後に亀裂や傾き、地震によって大仏の首が落下するという事故がありました。首の落下はすぐに修理がされましたが、その後も2回、焼失することになります。
1回目の焼失は平安時代末期で、東大寺内の建物の多くが焼失しましたが大仏及び大仏殿は共にほどなく再建されました。そして2回目は戦国時代で、仏教への関心や財源が減ってきていたこともあり、焼失後も数十年復興が進まず大仏が雨ざらしで放置されている状態でした。
2回目の焼失後、江戸時代に入ってからやっと費用が集まり再興され、1692年に大仏の開眼供養、1709年に大仏殿の落慶が完了しました。
頭部は江戸時代・体部は鎌倉時代の補修
2回もの焼失を乗り越えてきた奈良の大仏は、すべてが奈良時代当初のものではありません。修復を行う過程で、体の背中あたりは鎌倉時代、他の体部は室町時代末期、頭部は江戸時代に作られたものに置き換わっています。
奈良時代に作られて以降現在まで残っているのは、台座や足の一部です。また大仏本体の他、大仏殿前にある「金銅八角燈籠」についても、奈良時代のままの姿を残していると言われています。
「明治大修理」「昭和の大修理」
明治維新後も、東大寺の大仏殿は2回、修理されています。明治時代に行われた「明治大修理」は11年の長期間に及ぶもので、大仏殿の屋根を支える鉄骨を入れるなどして構造の強化を目的としたものでした。
そして、昭和49年から6年かけて行われた「昭和の大修理」では大仏殿の屋根の瓦を葺き替えるために約10万人以上が関与する工事が行われました。
現存の大仏殿は「世界最大の木造軸組建築」
2回の焼失と再建、明治と昭和の大修理を経て現在に残る東大寺の大仏殿は「世界最大の木造軸組建築」であり、中に置かれている大仏同様、国宝に指定されています。創建当初に比べると幅が約3分の2となっていますが、それでも最大です。
大仏をしっかり守る役割として建てられた大仏殿ですが、現在もその威風堂々とした姿で観光客を惹きつけています。
奈良の大仏の秘密
全国的に有名な奈良の大仏ですが、あまり知られていない秘密ポイントもあります。大仏の秘密として知っていれば、観光の際も単に見るだけでなく意味をもって鑑賞出来る、大仏の豆知識について4点ご紹介していきます。
大仏は年に2回窓から顔を出す
まず最初の秘密ですが、奈良の大仏は大仏殿の中に配置されているため、普段は外から見えることはありません。しかし、年に2回、大仏殿の窓が開けられ外からでも奈良の大仏の姿が拝める日が存在します。
大仏殿正面の窓が開けられるのは元旦と、「万灯供養会」という8月15日に行われる儀式の日です。新年の空気の中、またはたくさんの燈籠の明かりの中で見える大仏のお顔は、いつもと違った見え方が新鮮だと観光客からも好評です。
巻き毛のような「螺髪」は492個
大仏の頭、正確には髪型は何故あんなにぐるぐるした形なのかと思ったことはないでしょうか。小さい渦巻がいくつも乗ったような髪型は「螺髪(らほつ)」と言い、細かく巻かれた髪の毛が集まった状態です。
奈良の大仏の螺髪は、1つあたりの大きさが直径22cm、高さが21cm、重さが1.2kgであり、修復などを経て現在残っている螺髪の数は483個とされています。
手に水かきがある
ついつい顔を見てしまう大仏ですが、その手にも秘密があります。指と指の間の部分をよく見てみると、水かきのようなものがあり、「手足指縵網相(しゅそくしまんもうそう)」と名付けられています。
ただ特徴を出したいがために水かきのようにしているわけではなく、仏教的な秘密が隠されています。仏様の手を水かきのようにすれば、水をこぼさないで済むように、多くの人々を救うことが出来る、ということから特殊な手の形が作られています。
おでこのほくろは実は産毛
大仏のお顔を見ていて不思議に思われる部分として代表的なのが、おでこのところのほくろのような部分です。これも大仏に隠された秘密ですが、実はあの部分はほくろではありません。「白毫(びゃくごう)」という名前の、産毛が巻かれたものというのがその正体です。
白毫は、それがあることで光を放ち、世界を照らすことが出来るものとして眉間の中心に付けられています。仏像によっては宝玉がはめ込まれることもある白毫ですが、奈良の大仏は本体と同じ素材です。
知ると理解が深まる大仏の秘密ですが、実際に秘密となっている部分をこの目で見に行くもよし、同行した人に豆知識として披露するもよし、秘密として知っているだけでも楽しめます。
奈良の大仏周辺の観光スポット
奈良の大仏について、歴史や秘密など様々な面からご紹介しましたが、大仏を見た後はせっかくですから他の観光スポットにも行ってみましょう。大仏がある東大寺の中や周辺のお寺など、奈良は観光スポットには事欠かないので、観光コースを組むのも旅の楽しみになります。
ここからは、大仏の鑑賞と合わせて楽しめる、奈良の大仏周辺の観光スポットについてご紹介していきます。
「東大寺」
まずは、大仏のある東大寺全体についてのご紹介です。大仏だけ見て終わるにはもったいない見どころだらけのお寺で、境内には様々なお堂があります。東大寺の中だけでも国宝に指定されている建造物が何件もあり、じっくり見て回りたいものが盛りだくさんです。
「二月堂」
2005年に国宝にも指定された建物で、旧暦2月の時期にお水取りという行事が行われることから「二月堂」と名前が付けられました。境内全体の中では北東部に位置し、大仏殿からは少し離れています。
お水取りの期間は松明を振りかざす儀式が行われるので、観光で訪れる時期と合うのであればぜひ見てみましょう。
「戒壇堂」
「戒壇堂」は、仏教における戒律を授ける場として作られた建物で、東大寺の戒壇堂は県の重要文化財に指定されています。戒壇堂も大仏殿や他のお堂と同様、火災で一度焼け落ちていますが江戸時代に再建された建物です。
戒壇堂の位置は東大寺の境内において西側にあるので、アクセスの関係上西側から入る人や、お堂を回るコースによっては大仏殿より先に戒壇堂を見ることになります。
| 住所 | 奈良県奈良市雑司町406-1 |
| 電話番号 | 0742-22-5511 |
「春日大社」
仏教のお寺が多い奈良ですが、神社も有名なところがあり、世界遺産にも含まれている春日大社はぜひ訪れておきたい観光スポットです。厄除けの御利益や、重要文化財にも指定されている美しい廻廊など、見どころや楽しめるポイントでいっぱいの神社です。
境内には自然豊かな場所もあるので、のんびり緑を眺めながら歩きたいという人にもぴったりです。歴史も自然も両方満喫したいのであれば春日大社をおすすめします。
| 住所 | 奈良県奈良市春日野町160 |
| 電話番号 | 0742-22-7788 |
「興福寺」
多くの国宝を有し、立派な五重塔でも知られている興福寺も、東大寺に近くおすすめの観光スポットです。興福寺も境内が広く、かつそれぞれのお堂と仏像や歴史資料を収めた国宝館があり、じっくり見ているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。
簡単にでも観光したいのであれば、2018年に復元されて綺麗な姿となった中金堂や、国宝の五重塔をさっと回るコースがおすすめです。
| 住所 | 奈良県奈良市登大路町48 |
| 電話番号 | 0742-22-7755 |
「奈良公園」
奈良と言えば鹿を連想するくらい、鹿は奈良と馴染みのある動物です。鹿がたくさんいるところとして、一度見てみたいのが奈良公園です。奈良公園は面積が660ヘクタールもあることもあり、奈良で有名な各寺社仏閣にアクセスしやすい位置にあります。
雄大な自然が広がる奈良公園内には1200頭近くもの鹿が生息しており、ゆっくり眺めたり鹿せんべいを食べる様子を観察したりして、のんびり過ごせます。観光コースの合間に組み込んでも良いでしょう。
| 住所 | 奈良県奈良市春日野町 |
| 電話番号 | 0742-22-0375 |
奈良の大仏を含めたおすすめモデルコース
いくつもの寺社仏閣が集まる奈良へ行くなら、観光サイトなどの情報を参考にしたモデルコースを回ると効率良く見たいところへ行くことが出来ます。奈良の大仏を中心として、どのようなおすすめコースがあるのでしょうか。
世界遺産を巡る
観光コースと行っても目的や行く人のコンディションに応じて様々なコースがありますが、最も王道とも言えるのが世界遺産を中心に回るコースです。奈良で世界遺産となっている寺社仏閣を回ることで、歴史好きや奈良独特の雰囲気を感じて過ごしたい人にとって有意義な旅行となります。
奈良では「古都奈良の文化財」として8つの資産が世界遺産として登録されていますが、1日ですべて回ろうとするコースはどれも中途半端になってしまったり距離の関係上時間を無駄にしたりしかねないので、あまりおすすめしません。
そこで、コースとして効率が良く、様々な観光スポットを回ることが出来る内容としておすすめしたいのが、「興福寺」→「春日大社」→「東大寺(大仏殿)」→「二月堂」→「戒壇堂」という順番で回るコースです。
興福寺からスタートして、周辺を大きく1周回るようなコースとなっているので無駄に行ったり来たりする距離が少なく、途中は春日大社や奈良公園の自然も堪能しながら、充実した観光が可能となります。
ただし、どうしても長い距離を移動することになるので、気づかないうちに疲労がたまることもあります。時間や体力と相談しながら、モデルコースとして検討してみてください。
奈良の大仏を拝観して古の時を感じよう
奈良の大仏は、日本人が一度は見たことのある観光スポットであり日本でも最も知られた仏像ですが、大人になってもう一度見るとまた違った味わいのあるものでもあります。
子供の頃に見たことがある人も、初めて奈良へ行く人も、奈良の大仏の歴史や秘密を知った上で拝観し、奈良時代に大きな願いを込めて作られた大仏を見ることで、昔から続く人の思いや仏像の奥深さを感じてみてください。
![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)