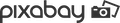本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。
石鎚山とは?
石鎚山は愛媛県の西条市と久万高原町の境目に位置する山です。地元では「いしづちさん」と呼ぶことが多いですが、「いしづちやま」とも呼びます。
さらに漢字表記も「石鎚山」「石土山」「石鉄山」「石鈇山」と複数ありますし、かつて愛媛県が伊予と呼ばれていたことから「伊予の高嶺」とすることもあります。
西日本最高峰!日本七霊山のひとつ!
石鎚山は標高1982mを誇る西日本最高峰の山です。ただし「石鎚山」という山が存在するのではなく、天狗岳・弥山(みせん)・南尖峰(なんせんぽう)の総称として「石鎚山」と呼んでいます。
3山の中で最も標高が高いのが天狗岳と南尖峰の1982mですが、弥山も標高1974mあるので、いずれにしても西日本最高峰の山といえます。
そんな石鎚山は、西日本地域における山岳信仰の拠点として古くから信仰の対象とされ、修験道(山岳信仰)では石鎚山のことを「霊峰石鎚山」と呼びます。
なお山に囲まれた日本では山岳信仰が庶民の間でも広く浸透しており、その中でも日本七霊山を参拝することが一大ブームになった時代があります。
日本七霊山とは富士山(静岡県・山梨県)、立山(富山県)、白山(石川県・岐阜県)、大峰山(奈良県)、釈迦ヶ岳(奈良県)、大山(鳥取県)があり、これらのそうそうたる名山・霊峰の中に愛媛県の石鎚山も含まれています。
そんな石鎚山が山岳信仰の修行道場として全国に名が知られるようになったのは、奈良時代のことです。しかもこの頃には修験道の開祖・役小角(えんのおづぬ)や空海が、石鎚山で修業をしたと記録があります。
日本仏教で大きな存在感を示した2人の名僧が修行した地ということもあり、石鎚山には修験道の聖地とされてきました。そしてその宗教活動の拠点となったのが、石鎚神社を含む4社です。
明治時代に行われた神仏分離政策によって組織の分離や改名などはあったものの、修験道の発祥から現在に至るまで修験道の聖地および修行道場であることに変わりはありません。
![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)