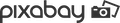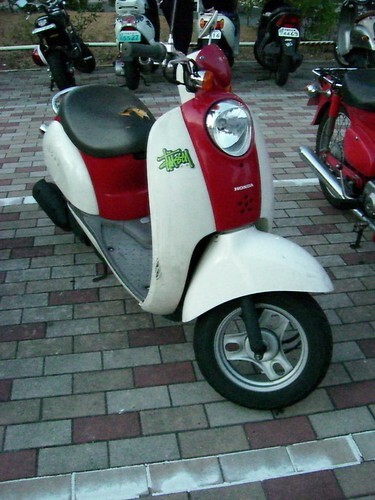本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。
レインボーブリッジは自転車通行できる?
芝浦エリアと台場エリアを結ぶ東京のレインボーブリッジといえば、映画のロケ地にもなった人気の観光スポットです。
もともとレインボーブリッジは千葉・神奈川方面から東京都心への交通分散と、箱崎・江戸川ジャンクションや首都高速羽田線で起こる慢性的な渋滞の緩和のために、1993年に開通した連絡橋です。
そのためレインボーブリッジの利用は圧倒的に車が多いのですが、実は車両が通行する道路の下には「レインボープロムナード」と呼ばれる歩道があります。
車の場合は有料の首都高速道路と無料の一般道路の2種類がありますが、歩道であるレインボープロムナードの通行は無料です。そのためフォトスポットとして訪れる人や、ウォーキングやジョギングを楽しむ人に人気があります。
レインボーブリッジを自転車で通行できるのは遊歩道
徒歩での通行が可能なレインボーブリッジでは、自転車の通行も可能です。レインボーブリッジには無料で通行できる歩道・レインボープロムナードがありますが、そのほかにも通行無料の一般車道があります。
そこで問題となるのが「自転車は歩道と一般車道のどちらを通行すればいいか?」です。現在の車両区分だと自転車は軽車両になるので、自転車に乗って(またがって)通行する場合は、車と同じく車道を通行しなければいけません。
ですから一般的な自転車通行のルールに基づけば、レインボーブリッジを自転車で通行する場合は無料の一般車道を利用することになります。
ところがレインボーブリッジの場合、一般車道を自転車で走行(自転車にまたがる行為)することはできません。この規定は、レインボーブリッジの歩道を走行する場合も含みます。
その理由はレインボーブリッジには非常に急な坂があるからです。自転車はペダルをこぐことで加速する乗り物ですが、下り坂ではペダルをこがなくても自然とスピードが上がります。
ところがレインボーブリッジにある急な坂はあまりにも傾斜角度がきついため、自転車で走行すると大事故を引き起こす可能性があるほど危険です。そのためレインボーブリッジでの自転車走行は禁止されています。
自転車での走行を禁止するほど危険な坂を作ってしまった理由は、レインボーブリッジの下を豪華クルーズ客船「クイーン・エリザベス2」を通過させる計画があったことと関係します。
当時「豪華クルーズ客船の象徴」ともいわれたクイーン・エリザベス2は、長さ293.6m、高さ52.2mの巨大なクルーズ船です。そんな巨大クルーズ船がレインボーブリッジの下を通過するためには、橋の桁下を50m以上確保する必要がありました。
ただしレインボーブリッジは羽田空港の制限空域内にあったため、クイーン・エリザベス2を通過させるための高さを十分に確保できませんでした。
とはいえ大型クルーズ客船が停泊できる東京国際クルーズターミナルの整備計画が上がるまでは、レインボーブリッジを通過させて埠頭へと誘導するルートが使われることになっていたため、大幅な高さの変更はできません。
そのためレインボーブリッジには自転車での走行が危険な急坂ができてしまい、そのことが理由で、一般車道の通行および自転車に乗ったままでの通行が禁止されたのでした。
遊歩道の距離は?
レインボーブリッジの歩道「レインボープロムナード」は、ノースルートと呼ばれる「北側遊歩道」とサウスルートと呼ばれる「南側遊歩道」の2ルートあります。
北側遊歩道は晴海・豊洲エリア側、南側遊歩道は東京湾・臨海副都心側にありますが、どちらも全長約1.7kmです。
北側遊歩道と南側遊歩道の間には、一般車道とゆりかもめ軌道があります。そのため歩道の反対側の景色を見ることはできませんし、レインボーブリッジの2つの歩道をつなぐ自転車用の連絡通路もありません。
ですから晴海・豊洲エリアの景色と東京湾・臨海副都心の景色を見たいのであれば、レインボーブリッジを往復することになります。ちなみにレインボーブリッジの歩道を往復した場合、移動距離は約3.4kmです。
ただし東京を代表する絶景スポットのレインボーブリッジなので、同じルートでも通行する時間によって表情が変わります。
晴れた休日の早朝は一般車道を通行する車も少ないので、さわやかな朝の空気を満喫しながら空中散歩を楽しむことができます。ところが陽が落ち街に明かりがともり始めると、ライトアップされた美しい都会の夜景に変わります。
このように通行ルートや時間によって景色が変わるレインボーブリッジの歩道は、徒歩で渡る人だけでなく、自転車で東京見物を楽しむ人にも人気です。
レインボーブリッジを自転車で通行する方法まとめ
ルートや通行時間帯によって様々な風景を楽しむことができるレインボーブリッジの歩道ですが、自転車で歩道を通行するためにはいくつかのルールがあります。そこでレインボーブリッジの歩道を自転車で通行するためのルールをまとめてみました。
自転車走行は不可
レインボーブリッジには危険な急坂があるため、自転車での通行は歩道のみ通行OKです。ただし自転車で歩道を通行する場合でも、自転車に乗って(またがって)通行することはできません。
自転車を徒歩で押していけばOKなのか?
軽車両に分類される自転車が歩道を通行する場合、自転車を押して徒歩で通行するのであれば通行OKが一般的です。もちろんレインボーブリッジの歩道も徒歩での移動が前提なので、「自転車を押して徒歩で通行する」であればOKなはずです。
ところがこの方法では、レインボーブリッジの歩道を自転車で渡ることはできません。正確にいうと「自転車を押して徒歩で渡るだけでは、レインボーブリッジの通行はできない」のです。
では輪行袋に自転車を入れ、荷物として抱えて徒歩で通行する場合はどうでしょうか?この場合は荷物(輪行袋)をもって徒歩で移動しているのと同じなので、通常の徒歩通行と同じ扱いになります。
ただし自転車を抱えて徒歩で1.7kmを移動する方法は、あまりにも過酷です。ママチャリの重量は平均20kgですし、ママチャリより軽いといわれる初心者モデルのクロスバイクでも、平均重量は10kgあります。
さらにレインボーブリッジの歩道には、自転車の通行を禁止する原因となった急坂があります。この急坂を平均10kg~20kgもある自転車を抱えて徒歩で移動するには、成人男性であっても相当な体力が必要です。
ちなみに大きな荷物を抱えていなくても、レインボーブリッジを徒歩で渡るには20分~30分かかります。ですからこの方法なら通行OKなのですが、一般的な方法とはいえません。
貸し出し専用台座が必要
自転車を抱えて徒歩で移動するなら通行OKのレインボーブリッジですが、体力に自信のない人や子供にはかなり過酷な方法です。ただしこのような大変な思いをしなくても、自転車での通行がOKになる方法があります。
実はレインボーブリッジでは、自転車を押しながら徒歩で移動する人のための専用台車が準備されています。専用台車は後輪に取りつけて使うのですが、装着した状態での自転車走行は禁止です。
専用台車とはいいますが、準備されているのは強度のある荷物運搬用の専用台車ではなく、木製の手作り感たっぷりな台車です。しかも固定方法も「マジックテープでまとめる」というかなりざっくりとした装着方法なので、ゆるみや段差などで外れてしまうことがあります。
さらに自転車に乗らないことを前提に作られているので、ルールを無視して自転車に乗ると、重みに耐えきれず壊れてしまいます。
そのため貸し出しの際には「ペダルに足をかけない」「外れたらその都度装着しなおす」など、厳しく注意されます。それでもこの方法であれば自転車を押して徒歩で移動がOKになるので、自転車でレインボーブリッジを渡るのであれば、このルールを守らなければいけません。
原動機付自転車(原付オートバイ)はOK?
自転車でレインボーブリッジを渡る方法は、まとめを読んでいただければイメージができたはずです。では自転車の仲間として区分される原動機付自転車(原付オートバイ)の場合はどうなのでしょうか?通行方法まとめの最後に、こちらも簡単に紹介しておきます。
電動機付自転車の場合、通常は一般車道を通行することが法律で決められています。ただしエンジンをかけていない状態であれば、電動機付自転車を押して歩道を通行するのはOKです。
ところがレインボーブリッジの場合、エンジンを切って徒歩で押す方法でも、原動機付自転車では通行することができません。
実はレインボーブリッジの原動機付自転車の通行禁止は、東京都公安委員会によって禁止されているのです。そのため自転車のように押して徒歩で移動する方法も、原動機付自転車には適用されないのです。
ただし「レインボーブリッジでの通行が禁止」は、すべての原動機付自転車が対象ではありません。原動機付自転車の種類は排気量によって決められており、レインボーブリッジでの通行規制も電動機付自転車の排気量で違います。
ちなみにレインボーブリッジの通行が禁止されているのは、排気量が50㏄以下の原動機付自転車が対象になっています。これは主に「原チャリ」と呼ばれているタイプのことなので、排気量が51㏄以上であれば、原動機付自転車でもレインボーブリッジの通行はOKです。
なお「原チャリ=スクーター」というイメージがあるかもしれませんが、スクーターと呼ばれる原動機付自転車がすべて原チャリの仲間とは限りません。
原動機付自転車には「第1種原動機付自転車」「第2種原動機付自転車」の2種類あります。排気量50㏄以下のものは、すべてまとめて第1種原動機付自転車に指定されているので、排気量50ccの原チャリは第1種原動機付自転車となります。
なお排気量51㏄~125㏄は「第2種原動機付自転車」なので、種別命に「原動機付自転車」とつきますが、レインボーブリッジが禁止する「排気量50㏄以下」には該当しないので通行OKです。
また名前にスクーターがつくビッグスクーターの排気量は250㏄を超えるので、レインボーブリッジも通行できます。この違いをできるだけ正確にわかりやすく説明すると、「スクーターの多くは通行OKだけど、原チャリはNG」となります。
レインボーブリッジで自転車通行・入り口はどこ?
「自電車でレインボーブリッジを通行する方法まとめ」で紹介した通り、自転車でも条件をクリアすればレインボーブリッジも通行OKです。そこでここからは、自転車通行・入口などをまとめて紹介します。
芝浦側
芝浦側を通行する場合は、北側歩道橋(ノースルート)を利用します。歩道からは芝浦ふ頭・東京スカイツリー・東京タワーなどが見えるため、東京観光の名所にもなっています。
日中はレインボーブリッジから遠く離れた東京名所も見えるため、東京の今を見学する観光客に人気です。ところが陽が沈むとになると華やかなイルミネーションと夜景が楽しめるため、大人のデートスポットに早変わりします。
なお北側遊歩道の入口は「芝浦口」です。芝浦口は芝浦ふ頭駅から5分の場所にある、ガラス張りの建物の中にあります。
自転車の場合は建物外側に「自転車専用」と書かれた矢印付きの案内看板があるので、看板の指示に従って建物の中へと進みます。
通行のために必要な自転車専用台車は、建物内にいるスタッフから受け取ります。なお台車本体と後輪をマジックテープでまとめるだけなので、装着時間はそれほどかかりません。
ただし自転車での通行に関する注意や説明があるので、実際に自転車でレインボーブリッジを渡るまでには少し時間がかかります。
台場側
台場側を通行する場合は、南側歩道橋(サウスルート)を利用します。歩道からはお台場海浜公園や芝浦のループ橋など、臨海副都心の景色が楽しめるため、子供連れやデートにも人気です。
なお南側歩道橋の入口は「台場口」です。お台場海浜公園駅からレインボーブリッジに向かって道なりに進むと、突き当りに台場口がある建物が見えてきます。
建物に入るための階段を上るとレインボーブリッジの南側歩道橋につながるので、徒歩で通行する場合はそのまま歩道に進みます。ただし自転車の場合は専用台車を取り付けなければいけないので、矢印看板の案内に従って自転車専用入口に進みましょう。
レインボーブリッジを自転車通行・所要時間
レインボーブリッジを自転車で通行する場合、自転車に乗って(またがって)の通行は禁止です。レインボーブリッジ歩道内に監視スタッフはいませんが、監視カメラが設置されているので、自転車に乗ればすぐにばれてしまいます。
しかも台車を取り付けた自転車を押しながら徒歩で渡るので、レインボーブリッジを渡るための所要時間は徒歩の場合と同じ20分~30分です。
ただしあくまでもこの所要時間は通行にかかる所要時間なので、台車の装着時間は含みません。また台車の貸し出しは無料ですが、貸し出しの際にはスタッフから通行に関する注意などをまとめて説明されます。
また台車を使わず輪行袋に自転車を入れて通行する場合も、袋に入れられるように自転車をまとめる(分解する・折りたたむ)作業があります。
ですから徒歩でレインボーブリッジを渡るだけなら20分~30分ですが、専用台車の装着・取り外しやスタッフの説明も所要時間に含まれます。そのため台車の装着などすべてまとめた所要時間は、少し長い40分~50分と計算するのがおすすめです。
レインボーブリッジで自転車通行・注意点
ここまではレインボーブリッジを自転車で渡る方法をまとめて紹介してきましたが、実際にレインボーブリッジの歩道を通行する際には、ほかにも注意しなければいけないことがあります。そこで通行中の注意点をまとめてみました。
遊歩道は人の往来があるので注意
レインボーブリッジの歩道は、あくまでも徒歩で通行する人のための通路です。そのため道幅もそれほど広くなく、自転車が2台横並びで通行すると通路がふさがってしまいます。
しかもレインボーブリッジ歩道のすぐ横は、車が走行する一般車道です。そのためイメージしている以上に車の音が大きく、ほかの歩行者から声をかけられても騒音でかき消されてしまいます。
さらにレインボーブリッジの歩道は、一方通行の歩道ではありません。自転車の場合は台場口からは南側遊歩道、芝浦口からは北側遊歩道のみの一方通行ですが、徒歩の場合はどちらの歩道を通行してもOKです。
しかも徒歩の場合は、自転車では利用ができない歩道橋を渡る連絡通路でレインボーブリッジを横断することもできます。そのため歩道では、歩行者同士が対面通行になる場面もあります。
そのうえレインボーブリッジの歩道には、市民ランナーの姿もあります。ですからレインボーブリッジを自転車で通行する場合は、歩行者・ランナーなど往来の多い歩道であることを意識しながら通行するようにしましょう。
歩いている人や時には車イスの人もいる
レインボーブリッジの歩道は、車いすでも通行できます。車いすで通行する場合は介助者が必要ですが、自転車のような特別なルールはありません。
車いすには手動と電動の2種類あり、横幅はJIS規格で決められています。なお車いすの横幅は手動の車いすなら630mm以下、電動式車いすだと700mm以下です。
ちなみに自転車の横幅もJIS規格で決められており、大人用の自転車の場合は600mm以下なので、手動・電動問わず車いすの方が自転車よりも横幅があります。
さらに車いすは徒歩の場合と同じくどちらの方向にも通行が可能なので、自転車と車いすが狭い歩道上ですれ違うことも考えられます。
もちろんこのようなケースでは、自転車・車いすの双方が配慮しあいながら通行するのが理想です。ただし風の影響を受けやすいレインボーブリッジでのできごとなので、できるだけ車いすの通行を優先するように心がけましょう。
風が強いので体力を消耗する
全長約1.7km、徒歩だと20分~30分で渡ることができるレインボーブリッジですが、海の上にかけられた連絡橋なので風を遮るものはありません。
しかも陸上では風がほとんどない日でも、海の上では強い風が吹くことがあります。このような状態では、風にあおられないように自転車を支えるだけでも体力を消耗します。
しかもレインボーブリッジには、自転車の走行が危険と判断されるほどの急坂があります。そのため坂を自転車を押して歩くだけでも大変ですし、レインボーブリッジを往復するとなれば体力の消耗は2倍になります。
ですから行きだけ(往復しない)の通行にしたり、入口にある駐輪場に自転車を停め徒歩で通行したりするなど、体力と相談しながらプランを計画するのがおすすめです。
レインボーブリッジで自転車通行・通行可能時間
車でレインボーブリッジを渡る場合は24時間通行OKなのですが、自転車での通行ができる歩道には、通行時間があらかじめ決められています。
しかも歩道の通行時間は時期によって異なるため、通行する前に確認するのがポイントです。なお4月1日~10月31日は9時~21時ですが、11月1日~3月31日は10時~18時と時間が短縮されます。
なお海から高い位置にあるレインボーブリッジの歩道には、風や雨を防ぐための壁はありません。(安全確保のための柵は設置されています)
そのため天候状態によっては利用時間内でも通行禁止になりますし、メンテナンス工事が行われる場合も通行できません。ですから当日の利用状況などが気になる場合は、事前にレインボープロムナード管理事務所または公式ホームページでチェックするようにしましょう。
レインボーブリッジを自転車で渡ってみよう!
レインボーブリッジを自転車で通行する方法や注意点をまとめて紹介しましたが、徒歩で通行するからこそ楽しめる魅力もたくさんあるのがレインボーブリッジです。自転車の場合は徒歩通行よりも面倒なことが多いですが、ルールを守って安全にレインボーブリッジからの景色を楽しんでください。
![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)