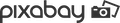本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。
「のれそれ」ってなに?
細長くて体が透き通っている不思議な生き物は、高知県名物「のれそれ」という魚です。体が透明な魚といえば深海魚をイメージする人も多いですが、高知県名物ののれそれは深海魚ではありません。
実は穴子の稚魚のことを高知県では「のれそれ」と呼んでおり、古くから高知県民によく知られた旬食材です。ただし「穴子の稚魚=のれそれ」なので、穴子の生育地の周辺以外では食べ方だけでなく名前もほとんど知られていません。
なおのれそれのような不思議な姿をした稚魚のことを「レプトケファルス幼生」というのですが、穴子だけでなくウナギ・ウツボなどの仲間も稚魚の段階ではレプトケファルス幼生になります。
成魚になると見た目・形・色などが全く異なる魚たちですが、レプトケファルス幼生の段階では「平たくて長い」「透明な体」「ゼラチン質」の3つが共通しています。
たとえば穴子とよく似たウナギを例にして、レプトケファルス幼生から成魚までの成長過程と体の変化を説明しましょう。
ウナギの産卵地は判明されていませんが、南方系の海で産卵されていることは確認されています。孵化するとまずレプトケファルス幼生になり、黒潮にのって日本の近くまで流されます。
このときに役立つのが、レプトケファルス幼生特有の葉っぱのような体です。この体のおかげでウナギのレプトケファルス幼生は、はるか遠い南方の海から日本のすぐ近くまで泳がずに移動ができます。
孵化した海から日本沿岸まで北上する過程で、ウナギのレプトケファルス幼生はシラスウナギに変態します。つまりウナギの稚魚としてよくしられているシラスウナギは、レプトケファルス幼生が成長したものなのです。
なおシラスウナギに変態する過程で、レプトケファルスの特徴であるゼラチン質の体は体組織へと変わります。これはゼラチン質が脱水・収縮することによって起こるので、水分が抜けたシラスウナギは身がしまり体も小さいです。
穴子の稚魚であるのれそれも、ウナギの成長過程と同じです。孵化後は潮の流れで生育地の近くまで移動し、成魚に変態する頃にはよく見る穴子の姿になって産卵のために川をのぼります。
このようにおもしろい成長過程をたどる穴子の稚魚・のれそれは、稚魚の間しか食べることができない時期限定の幻の食材なのです。
高知県で名物の珍味!
漁業技術が発達している今では一般家庭でも食べることができるのれそれですが、水揚後の鮮度を保つのが難しいため、かつては産地の高知県でも漁師しか食べられませんでした。
その後技術の発達により徐々に市場に出回るようになると、産地である高知県では一般家庭の食卓に並ぶほどメジャーな食材になります。
なおのれそれと呼ばれる穴子の種類にはいくつかあり、のれそれが名物の高知県では主に穴子とクロ穴子の稚魚が大半を占めます。
とはいえのれそれは、産地の高知県でも旬の時期にしか食べられない珍しい魚です。成魚に変態する前にとれたものしかのれそれにはなりませんし、のれそれを専門に漁獲する漁もありません。
さらに遠い南方の海で生まれたのれそれが、どのようにして日本にやってくるのかもよく分かっていません。そのため名物としている高知県でも食べれる時期や量が限られるため、「高知県名物の海鮮珍味」と呼ばれています。
穴子の稚魚「のれそれ」の旬の時期は?
穴子の産地でもある高知県では昔から有名なのれそれですが、全国的な知名度のある魚ではありません。そこで「高知県名物の海鮮珍味」と呼ばれるのれそれの旬の時期などを詳しく紹介します。
旬は早春!のれそれ以外の呼び方も?
主な産地である高知県ではイワシシラス漁やパッチ漁(汽船船曳網漁)の網にまぎれてとれるため、早ければ1月頃からとれはじめ、5月末ごろま水揚げされます。
ただしのれそれの旬は2月~4月の早春なので「春を告げる食材」といわれ、産地の高知県では家庭の食卓にも旬のれそれが並びます。
そんな高知県では昔から「のれそれ」の名前で呼ばれているので、出荷される際も一般的に「のれそれ」と呼びますが、地域によっては別の名前で呼ぶことがあります。
たとえば兵庫県淡路島周辺では、のれそれのことを「はなたれ」と呼びます。漢字で書くと「洟垂れ」なので、高知県名物のれそれの別名にしては残念な名前です。
ほかにものれそれの産地である岡山県では「べらた」という名前で呼ばれており、高知県ののれそれと同じく早春を告げる名物食材として知られています。
ちなみに岡山県には瀬戸内海につながる吉井川・旭川・高梁川の三大河川がアナゴの生育地となっているため、地元では古くからのれそれを食べる習慣があります。
ただし岡山県ののれそれは、瀬戸内海に出たアナゴが産卵のために三大河川へ戻ってくるのが2月~3月なので、とれる時期・旬ともに2月~3月です。
なお兵庫県淡路島の「はなたれ」や岡山県の「べらた」の名前の由来はよくわかっていませんが、高知県ののれそれは、網にかかったときののれそれの様子に由来するといいます。
高知県名物ののれそれですが、のれそれ漁というものはなく、ほかの魚の網にかかったのれそれをとるのが一般的な漁獲方法です。
網にかかったのれそれは想像以上に生命力が強いため、一緒にとれたほかの魚が死後硬直していても元気に動き回ります。そのためほかの魚の上を乗ったりそれたりしながら逃げ回る様子から「のれそれ」と呼ぶようになったといいます。
「のれそれ」の食べ方①生で
高知県名物・のれそれを味わうなら、シンプルに生で食べる方法が1番美味しいです。穴子の稚魚なので、旬の時期を過ぎるとのれそれの透明な体は茶色に変色しますし、加熱しても白っぽくなります。
のれそれは見た目の珍しさも魅力の1つなので、透明なのれそれを生のまま食べるのは、味だけでなく目でも楽しめる最高に贅沢な食べ方です。
のれそれは鮮度が命!踊り食いもおすすめ
生命力が強いのれそれですが、鮮度が落ちると生で食べるのは難しいです。「生で食べられる=鮮度がよい」という証拠ですから、のれそれを食べるなら、まずは刺身からにしましょう。
のれそれの刺身えは、最初に舌触りの良さを味わいます。体の大部分がゼラチン質なので、のれそれを口に入れるとつるりとした舌触りがあります。
大きさによっても刺身の盛り付け方が変わりますが、平均サイズは5cm前後なので小鉢などに盛り付けるの一般的です。
なおのれそれの中には、体長が約10cmの大型もあります。このサイズののれそれは値段がやや高いので、あえて長さがわかるようにして盛り付けることがあります。
このような盛り付け方だと一瞬ぎょっとするかもしれませんが、骨もまだ出来あがっていない穴子の幼魚なので、のれそれそのものの見た目に驚くことはありません。
食感はプリッとした感じが印象的です。高知県民にのれそれの食感について尋ねると「ところてんに近い食感」といいますが、この表現はのれそれの食感の特徴をよくとらえています。
なおゼラチン質の体なので、2~3回噛むと簡単に飲み込めます。噛んでいる時にはそれほど味の主張がないのれそれですが、のどを通って行く時にほんのりとした甘みと磯の香りを感じます。
この独特の味と風味を楽しめるおすすめの食べ方が「のれそれの踊り食い」です。のれそれの踊り食いは活きたままののれそれを食べるので、産地である高知県内でもなかなか食べられません。
ただしのれそれのストレートな味と独特の舌触り・食感を味わうなら、刺身より踊り食いの方に軍配が上がります。
なお踊り食いはのど越しの良さが楽しめる食べ方なので、わさび醤油よりもポン酢につけて食べる方がおすすめです。ちなみに地元・高知県では、塩少々とゴマ油を混ぜてつける食べ方もあります。
新鮮な生ののれそれは、沖付けにする食べ方も人気です。沖付けという食べ方はもともと漁師飯の1つで、自家製の漬けだれを船に持ち込み、とれたばかりの魚の切り身を漬けだれにつけて食べたのが始まりといいます。
沖付けの名物といえば「いかの沖付け」がありますが、「沖でつけた食べ物=沖付け」なので、食材が違っても調理法が同じであれば沖付けと呼びます。
なおのれそれを沖付けにすると、数時間で透明な体が醤油ベースの漬けだれ色に染まります。また中まで醤油の味がしみこんでいるので、ほんのりとしたのれそれの甘みと醤油の風味がマッチして美味しいです。
美味しい高知県の地酒に合わせるなら、のれそれの味噌和えもおすすめの食べ方です。のれそれの刺身に特製の味噌だれを添えると、シンプルなのれそれの刺身も味わえます。
食べ進めながら味噌だれと少しずつ混ぜていくと、色が少しずつ変わってくるので目でも楽しめます。またのれそれの味噌和えをご飯にのせて締めにする食べ方も人気です。
「のれそれを食べるなら穴子とセットで楽しみたい」という場合は、のれそれの旬の時期に地元の寿司屋を訪ねるのがおすすめです。
新鮮なのれそれがとれる地域は穴子の産地でもあるので、地元の寿司屋では上質な穴子の寿司と穴子の稚魚・のれそれの寿司の2種類が食べれます。
なおのれそれは軍艦巻きにするのが一般的で、たっぷりののれそれにすりおろししょうがとネギを添えれば、初春を告げるのれそれ寿司の完成です。癖のないのれそれはすし飯との相性がよく、後味もさっぱりしています。
「のれそれ」の食べ方②加熱調理
旬ののれそれは刺身など生で食べるのが1番美味しいのですが、加熱調理する食べ方も産地の高知県では人気です。
卵とじや茶わん蒸しにも
生のままでも美味しいのれそれですが、卵とじにするとさらに旨味が増します。春を告げる旬食材なので、同じく春が旬の菜の花と一緒に卵とじにすると目にも鮮やかな一品料理になります。
シラスなどの稚魚だとやや臭みが気になる人もいますが、のれそれは臭みそのものがないので加熱調理しても風味が変わることがありません。
透き通るような身は加熱すると白色に変わり、卵の黄色・菜の花の緑・のれそれの白の3色が程よいバランスでミックスされるので、見た目にも美味しい食べ方です。
のれそれの卵料理は、和風だけでなく洋風の食べ方もおすすめです。特に小さなお子さんがいる場合は、たっぷりの卵に新鮮なのれそれを混ぜて焼くだけで美味しいのれそれオムレツができます。
また半熟の状態でフライパンから取り出し熱々のご飯の上にかければ、半熟卵とのれそれの卵どんぶりの出来上がりです。この食べ方なら、忙しい時でも簡単に旬ののれそれを味わうことができます。
時間をかけて美味しいのれそれ料理にチャレンジするなら、具にたっぷりとのれそれを使った茶碗蒸しはいかがでしょうか?
のれそれそのものは癖のない魚ですし、加熱調理することで甘みが増しますがしつこい甘さではないので、茶わん蒸しのほかの具材と味でぶつかり合うことがありません。
春を告げる食材とはいえ、のれそれが旬を迎える早春は肌寒い日が続きます。そんな時に食べるのれそれの茶わん蒸しは、冷えた体を芯から温めてくれる贅沢なごちそうです。
番外編ですが、のれそれを熱々のうどんの上にトッピングする食べ方も地元では人気があります。のれそれは平たい麺のような形をしているので、熱々のうどんの上にのせるだけで簡単に火が通ります。
そこにのれそれと相性のよい卵を合わせると、黄身の濃厚な味が淡白なのれそれに絡まりさらに美味しくなります。また時間がたつと少しずつ食感が変わってくるので、火の入り具合によって変わるのれそれの魅力が楽しめます。
「のれそれ」を味わえる居酒屋はこちら
のれそれの旬の時期になると、町の食堂などでも「時期限定メニュー」としてのれそれ料理が提供されます。しかしせっかくの海鮮珍味ですから、美味しいお酒と一緒に味わいたいのでは?そこでのれそれの旬の時期におすすめの居酒屋を2店舗ご紹介します。
藁焼き鰹たたき明神丸 ひろめ市場店
藁焼き鰹たたき明神丸 ひろめ市場店は、高知県の名物料理がずらりと並ぶ高知市のフードコート「ひろめ市場」にある居酒屋です。
店名にもある通り藁焼き鰹たたき明神丸 ひろめ市場店の名物は、高知県民のソウルフードである藁焼きかつおたたきで、フードコート内にある居酒屋ですが店頭で豪快に焼く藁焼きかつおたたきを目当てに平日でも多くの客が訪れます。
この店では高知県土佐地方で伝わる伝統の一本釣りで釣りあげたかつおを使っているだけでなく、注文されてから藁焼きにする徹底ぶりです。
そのためかつおの味にうるさい高知県民の間でも人気の居酒屋で、仕事帰りに名物のかつおたたきをつまみに立ち寄るサラリーマンの姿が多く見られます。
グランドメニューには、高知県土佐名物のかつおたたきメニューがずらりと並びます。かつおたたきは単品から注文ができ、塩とタレの2種類からお好みで選ぶことができます。
なおフードコート内にある居酒屋なので、ランチ営業も行っており、食事系メニューにはかつおたたき定食と3種類のかつおたたき丼があります。
かつおたたき定食は、かつおたたきの数によって少・中・大の3種類があり、大定食だと名物のかつおたたきが10切れにご飯とみそ汁がついて1520円です。
お店自慢の塩かつおたたきも食べたい人には、塩・タレの両方が味わえる「かつおたたき塩・たれ定食」がおすすめです。塩・タレそれぞれ5切ずつにみそ汁とご飯がセットで1570円なので、単品でビールをつけても2000円で食べれます。
なおお目当てののれそれは旬の時期が決まっているため、グランドメニューにはありません。また旬の時期であれば必ず食べれるとも限りません。
とはいえかつおの漁獲量トップクラスの明神丸が運営する店なので、時期になれば新鮮なのれそれが高確率でメニューに登場します。
ちなみに高知県民の間では「新鮮な魚介を手ごろな値段でお腹いっぱい食べれる定食屋」として有名な店なので、高知観光のランチスポットとしてチェックするのもおすすめです。
| 住所 | 高知県高知市帯屋町2-3-1ひろめ市場内 |
| 電話番号 | 088-820-5101 |
黒尊
「美味しい高知名物をお腹いっぱいに食べてほしい」という店主のサービス精神が料理に反映していると人気の居酒屋です。店主との会話が楽しめるカウンター席が人気の店なので、リピーターの多くが座敷席ではなくカウンター席を予約します。
基本的に店主のおまかせで料理が出てくるので、来店すると最初に食材や調理法の好みを確認されます。好みのリサーチが終わると、次々に店主自慢の料理が出てきます。
刺身の盛り合わせは、見た目の美しさよりもボリュームと食べたときの満足感を重視しています。もちろん旬の時期の食材を使っているので、鮮度や味は抜群です。
高知県名物のかつおたたきも、ほかの刺身と同じく1切れがとんでもなく分厚くカットされています。なお一緒に添えられるニンニクスライスも、ほかの店よりやや厚めです。
もちろんのれそれの時期になると、のれそれの刺身が出ることもあります。ただし基本的に店主のおまかせで料理が出てくるので、どうしてものれそれを食べたい場合は、予約の際にのれそれの入荷状況を確認するとよいでしょう。
のれそれも時期限定の名物メニューですが、四万十川の天然アユの塩焼きも時期限定なので人気です。川魚は独特の臭みがあるため苦手な人も多いですが、黒尊では新鮮な天然アユを使っているので臭みはまったくありません。
脂がたっぷりとのった肉厚の天然アユですが、鮮度が抜群なので身離れがよく、最後まで気持ちよく食べれます。なおあくまでもおまかせ料理なので、値段は仕入れの状況などによって変わります。
ただしそうはいっても、まるまると太った四万十川の天然アユ2匹で、値段は1000円~1500円が相場です。そのため味・ボリューム・値段ともに満足できる居酒屋として、連日のように店内は地元客でにぎわっています。
| 住所 | 高知県高知市本町3-4-18 |
| 電話番号 | 088-873-2624 |
「のれそれ」を味わえる懐石料理のお店はこちら
早春を告げる海鮮珍味ですから、味だけでなく目でも春を感じられる懐石料理でのれそれを楽しむのはいかがですか?
のれそれは高知県名物なので、旬ののれそれを提供する懐石料理は数多くありますが、その中からとっておきのおすすめ店をご紹介しましょう。
高知座屋
JR高知橋駅から徒歩5分の位置にある「高知座屋(こうちいざりや)」は、旬の時期にしか食べられない食材や新鮮な魚介などをメインにした懐石料理の店です。
店内も落ち着いた和モダンな大人の隠れ家のような雰囲気で、美味しいお酒を飲みながら大切な人とゆっくり食事が楽しめます。
店は1階がコース料理のみのカウンター席で、2階はコース料理とアラカルトの2種類から選ぶことができる個室席になっています。そのためゆっくりと食事を楽しみたいときは1階、接待や宴会の場合は2階を選ぶのがおすすめです。
コース料理は地元でとれる新鮮な魚介や野菜が目にも鮮やかに調理されますし、食材に合わせて選ばれる器たちも料理のスパイスになっています。
高知県名物のかつおたたきもコース料理に含まれますが、そのほかにも旬の時期の海の幸・山の幸を使った懐石料理を準備しています。
なお「高知県で有名な懐石料理店」として地元でもよく知られている店なので、来店する時には予約をするのがおすすめです。
ちなみに高知座屋は電話予約OKの店なので、予約の際にのれそれの入荷状況を確認しましょう。のれそれが旬の時期でも入荷状況は日によって違うので、確実に旬の時期ののれそれを食べるには事前の確認が必要です。
高知名物を上質な空間で
初めての来店だと店内の豪華な雰囲気にしり込みしてしまうかもしれませんが、これは「五感すべてで食事を楽しんでほしい」という店主の想いが込められています。
確かに「気軽に立ち寄れるお店」というには値段がお高めですが、高級懐石料理店にありがちな堅苦しさはありません。料理はご飯が美味しく食べられるメニューが並んでおり、郷土料理をベースにした和洋折衷の懐石料理といった感じです。
なおコース料理の締めに出されるデザートも人気です。デザートメニューはコースの内容によって変わりますが、中には洋風デザートの盛り合わせもあるため女性客から人気があります。
| 住所 | 高知県高知市廿代町2-8 |
| 電話番号 | 088-824-1308 |
のれそれを高知のおすすめのお店で食べてみよう!
春の訪れを告げる旬食材・のれそれは、高知県民が大好きな春の食材です。鮮度が命の食材なので産地以外ではなかなか食べられませんが、のれそれが名物の高知県には美味しいお店がたくさんあるので、ぜひ足を運んで旬ののれそれを食べてみてください。
![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)