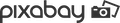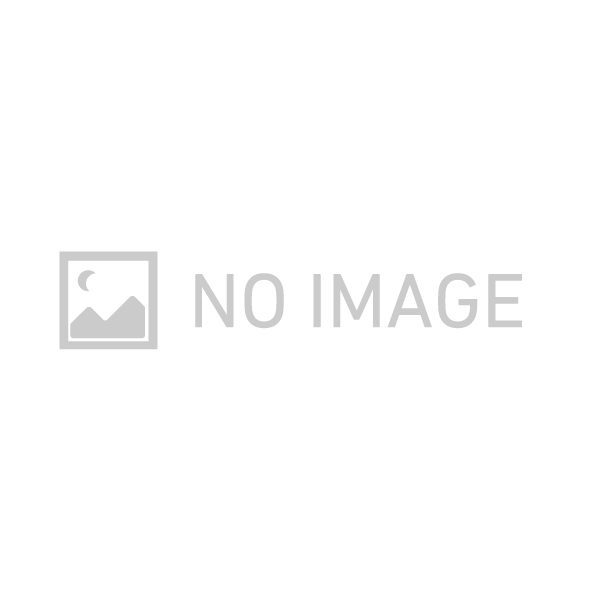本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。
安来節は島根県安来市の民謡
「安来節」は島根県安来市で生まれた民謡です。民謡自体を耳にすることが少なくなった現在、場合によっては安来節より「どじょうすくい踊り」のほうが通じやすいです。安来節が始まったルーツは約300年も昔に遡ります。大衆文化が発展し始め、歌や踊りが流行し始めた時代でした。
当時の島根県安来市は砂鉄や米などの物資を積み出す港として栄華をきわめていました。そのため国内各地から安来の港へ多くの船乗りが集まっていました。
船乗りらの交流により、「佐渡おけさ」や「船歌(ふなうた)」、「田植歌(たうえうた)」また「追分節(おいわけぶし)」など各地の民謡が盛んに交流されていました。このような背景が、安来の地に多様な民謡が根付くきっかけとなりました。
やがておさんという女性が歌った「おさん節」という民謡が、節の付け方や抑揚が独特で面白いと評判になります。それが安来節のベースになりました。さらに色々な歌い人により研鑽され、今の形へと進化を遂げていきます。
徐々に生活文化に広がっていった安来節は、地域の人々の宴席の場にて歌われ始め、楽しまれる民謡となりました。その飲みの席で「どじょうすくい踊り」が融合します。
酔いの回った若者たちが、どじょうをすくう仕草を安来節に合わせてその場のアドリブで踊り、仲間内で興じていました。これがどじょうすくい踊りの原点だと言われています。市民の普段の生活の中から生まれた表現でした。
船乗り達によって流入した民謡から始まり、時代と共に変わりながら安来節は出来上がっていきました。安来の人々の暮らしと一緒に、地方民謡として浸透していく過程を経たのです。
安来節の歴史
明治に入る頃に、安来節はお祭りで歌われるほど地域の生活に根付くものとなっていました。町内を夜通し練り歩きながら歌う「月の輪まつり」というもので、子供も大人も、男女の別もなく皆に親しまれる民謡となったといえます。
そして明治の終り頃、安来市に渡部お糸という歌の達人が出てきます。非常に芸達者な女性で、お糸の歌はとても評判が良く、技の素晴らしさは見る人を驚かせました。そしてお糸は安来節を一段と魅力的な芸能へと発展させていくことに貢献します。
大正に入る頃、渡部お糸は三味線の名人と共に一座を組み、全国ツアーを行います。芸術の域まで進化させた安来節を全国で披露していき、行く先々で大好評の結果でした。
安来節は渡部お糸一座により、日本中で人気を博していました。東京と大阪では専門の上演館まで立ち上がり、人々は安来節を鑑賞し喜びました。ついに日本中を席巻する民謡へと変わっていくのです。
若者が飲みの場で楽しむ歌と踊りから始まった安来節は、渡部お糸により日本中にその魅力が伝えられ、全国区の知名度へと押し上げられました。その後50年余りも日本人に愛され、全盛を極めます。日本にとどまらず、一座は朝鮮半島や台湾等のアジアにも安来節を広めました。
大正時代に人気であった安来節は、大手お笑い芸能プロダクションである吉本興業でも寄席として導入していたと言われています。
吉本興業の前進である吉本興業部は、従来の落語がメインでお客がつかず苦戦しているタイミングでした。そこに安来節を組み込むことで客足が伸び、勢いがつきました。実際に安来にまで足を運んで歌い手・踊り手を探し、大阪で興行した結果成功しました。
安来市から4人の踊り子を集めて安来節を披露する女性ユニットを結成するエピソードは、NHKドラマ「わろてんか」でも放送されました。
年に一度行われる安来節の資格審査会
安来節の伝統を守ることを目的として「正調・安来節保存会」がという団体があります。正調・安来節保存会には全国に約8500名もの会員が在籍しています。日本の伝統芸となった歌と踊りを後世に伝えるべく、安来節のイベントを開催しています。
正調・安来節保存会では年に一度「安来節資格審査会」を行い、「唄・絃・鼓・踊」の4つの部門に分けて審査しています。
それぞれの部門で新人は3級~3段まで階級があり、上は「准師範」・「師範」という最上位階級があります。会員は日々安来節の技術を磨き、最終的には「師範」を目指して毎年この資格審査会に挑戦しています。
また、毎年8月には一大イベント「安来節全国優勝大会」が開催されます。この全国優勝大会では、唄、絃(三味線)、鼓、踊、銭太鼓の5部門の日本一を決めるコンクールを行っています。
安来節全国優勝大会は3日間に渡って開催されます。正調・安来節保存会の各支部の予選大会を突破した「支部代表」が集まるこの大会は、毎年盛り上がりを見せています。
安来節との融合で発展した「どじょうすくい」
安来節といえば、どじょうをすくう仕草のコミカルな踊りが特徴的です。元々は安来の若者達が酒の席で、歌に合わせてアドリブでどじょうをすくう踊りをして皆で楽しんでいたものが始まりでした。
若者らは川でどじょうをすくい、すくったどじょうを肴に酒盛をするというのが定番でした。酔った酒の席では決まって、どじょうをすくう動作を真似た踊りをしており、皆で盛り上がり楽しんでいました。
地域の人々ですっかり定着したどじょうすくい踊りは、徐々に小気味よいリズムに形作られます。大衆の生活、特に宴席の場で融合していき、やがてお糸一座の活躍とも相まって、芸能として発展していきました。
「どじょうすくい」は、「土壌すくい」に由来しているという言い伝えもあります。出雲では砂鉄がよく取れたため、砂鉄をとる動作、つまり土壌から砂鉄をすくう振りであるという説です。
時を経て改良されていったどじょうすくい踊りは、やがて男踊りと女踊りに分けられ、客席でも楽しまれる踊りへと発展していきました。
どじょうすくい男踊り
男踊りは、ざるを使いどじょうをすくって酒の肴にする様子を、面白く踊りの姿にしたものです。踊りの最中に見せるチャーミングな笑顔が特徴的です。
カスリ着物にももひきを履き、鼻あて(もしくは鼻に割りばし)という恰好で踊ります。基本的な流れはありますが、決まった型はないため踊り手のオリジナリティが織り交ぜられます。
見た目はもちろんですが、腰を振りながら歩くコミカルな動作や愛嬌のある表情が魅力的です。見ている人を自然に笑顔にする楽しい踊りです。
どじょうすくい女踊り
女踊りは三味線の音に合わせて優美に、そして軽快に踊ります。女性もカスリ着物に小形のざるを持ちますが、男性の面白おかしい衣装とは違いキュートな姿です。踊り方も男踊りとは対照的です。滑稽な表現の男踊りとは違い、女踊りは女性らしい上品な仕草で、華やかに舞い踊る様が魅力的です。
安来節にかかせない楽器
歌と踊りの成り立ちや踊りの種類についてご説明しましたが、安来節の魅力はこれだけでなく、美しい伴奏を担う三味線等の楽器の存在も欠かすことができません。特徴的な伝統楽器をご紹介します。
大小を1人で打ち鳴らす独自のスタイル「鼓」
歌の伴奏に欠かすことができない鼓です。鼓は大小二つの鼓を一人で打ち鳴らします。これは歌舞伎の技法とは異なり、安来節独特な技法です。
元々は小鼓だけを膝の上に置いて器用に裏表を打ち鳴らし、それが曲打ちとして面白いものでした。後に大鼓を両膝に挟み、二丁打ちをするようになっていきました。大正初期に現在の大小二つの鼓を打ち鳴らすというスタイルになり、現在はこれが正式な姿勢と提唱されています。
高い技術の奥深い音色「三味線」
民謡の定番である三味線ですが、安来節の伴奏にも三味線が使用されます。三味線の独特な音色と音程は魅力を一層際立たせます。
安来節ではハヂキ、スクイ、スリ指といった三味線の演奏技術が駆使されます。安来節ならではの技術であり、三味線奏者はとても高い技術と鍛錬が必要とされます。
三味線の独自の演奏技術により、安来節の音色に奥深い余剰感を演出できます。そのためこの技術を習得した人は三味線の師範、大師範、准名人、名人という称号を与えられます。
どじょうすくいと人気を分ける「銭太鼓」
安来節になくてはならない存在である銭太鼓です。リズム楽器である銭太鼓は、踊りの伴奏として使用されます。銭太鼓は出雲地方の民俗芸能楽器の一種であり珍しい楽器です。
銭太鼓と呼ばれる楽器は日本に2種類あり、一つは縁に銭を取り付けた小太鼓と呼ばれるものです。佐賀県、青森県、埼玉県などの民族楽器として使用されます。
もう一つの銭太鼓は、棒状の筒のような形で竹でできており、中国、四国地方で使用されます。安来節の伴奏に用いられるのは、こちらの銭太鼓になります。
銭太鼓は「太鼓」と入っていますが、和太鼓のようにバチで叩いて演奏するものではありません。両端に銭が括り付けられていて銭が触れ合わせて音を出す楽器です。
銭太鼓を両手に持ちジャグリングのように回したり、打ち鳴らしたりして演技します。銭太鼓の銭の小気味よい音と、華麗な技で安来節を華やかに演出します。
銭太鼓を使った小気味よい音とキレのある動きの演技は迫力満点です。戦後以降、銭太鼓を使った演技は安来節の余芸として取り入れられ、魅力を際立たせる人気の芸です。
安来節の魅力がつまった「安来節演芸館」
安来市には安来節演芸館があります。安来節の殿堂と言われ、芝居小屋を彷彿とさせる外観は風情を感じます。安来市の代表的な観光スポットである安来節演芸館を紹介します。
安来節演芸館の基本情報
安来節演芸館は2006年に安来節を毎日鑑賞できる場所として創立された施設です。島根県の登録美術館である足立美術館と隣接しており、安来市の代表的な観光スポットとなっています。
演芸ホールは座椅子のような形の桟敷(さじき)席を模した作りになっており、このホールで安来節の生の歌と踊りを鑑賞することが可能です。公演は営業時間10時から17時の間に、毎日4回行っています。
安来節の名人の歌の後ろでは三味線や鼓の生の伴奏が響きます。コミカルな男踊りと舞踊のような上品な女踊りなどプロによる本物の芸を毎日見ることができる唯一の場所です。
安来節の通常公演の最後には「ちょこっと体験コーナー」があり、実際に衣裳を身に着けて、どじょうすくい踊りを踊れます。腰を上下に振りながら歩く動作は意外と難しく、名人芸の凄さを体験できます。
また演芸館では、安来節保存会本部道場の指導による各種教室も開かれています。唄、銭太鼓、どじょうすくい男踊り、どじょうすくい女踊り、絃、鼓などの種目を教えており、毎月第4木曜日に実施しています。各種教室は無料で受講できます。
安来節演芸館には、お食事処「どじょう亭」があります。安来どじょう、島田たけのこなど、市内で採れる食材を使った料理を提供しています。
どじょう亭おすすめの「まるごと安来丼」は、どんぶりでどじょう料理を食べられます。そのほかにも「どじょうのかき揚げ御前」など、安来のどじょうを使ったメニューがあります。
安来節演芸館には特産品を扱うお土産処もあるので、安来に来たお土産として安来の伝統工芸品やお菓子、安来節アイテムを入手することが可能です。
アクセス
安来節演芸館への車でのアクセスは、山陰道安来ICから県道45号線に出て、広瀬方面へ約15分で到着します。電車・バスでのアクセスの場合、松江駅から安来駅まで電車に乗り、安来駅から安来節演芸館までイエローバスで行くことができます。松江駅から安来節演芸館まで約50分で到着します。
| 住所 | 島根県安来市古川町534 |
| 電話番号 | 0854-28-9500 |
安来節体験道場で歌と踊りをマスター!
生の安来節を見て踊ってみたくなった方は、安来節演芸館に隣接している「安来節屋」に行きましょう。安来節屋の体験道場で、どじょうすくい踊りを実際に体験可能です。どじょうすくい体験道場では4歳から体験の参加が可能で、正調安来節保存会の名人が優しく、楽しく教えてくれます。
どじょうすくい体験後には、「ちょこっと名人終了証」をもらうことができるため思い出作りにも最適です。踊りの他にも銭太鼓や歌の体験も可能です。体験を終了すると、隣接する「さぎの湯温泉・どじょうすくいの湯」の無料入浴特典もついてくるためお得です。
また一度体験をすればどじょうすくい踊りをかくし芸として身に着けることもできます。時間は約40分で、事前の予約が必要となります。
| 住所 | 島根県安来市古川町467-5 |
| 電話番号 | 0854-28-6788 |
奥深さを知ればもっと安来節が楽しめる!
今回は島根県安来市で生まれた民謡、安来節についてご紹介しました。最近では見かけることが少なくなりましたが、歌と踊りそれから三味線や銭太鼓などの伝統楽器と、魅力がたくさん詰まった民謡です。歴史や魅力を知ることで安来節をより楽しむことができます。
![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)