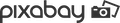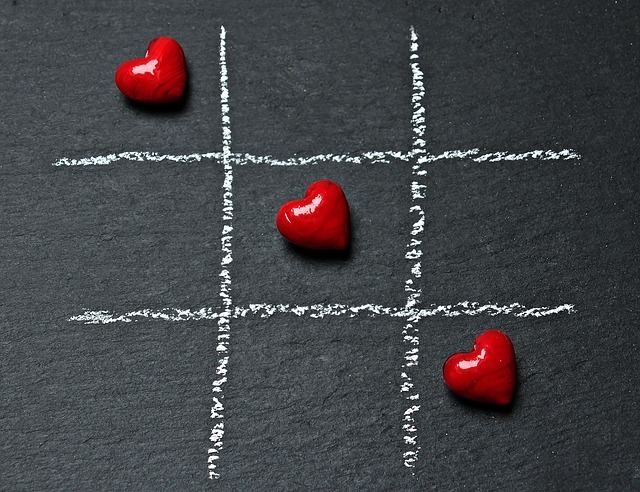本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。
佐賀県南部の有明海に接する歴史探索が出来るドライブのおすすめスポットは、国の特別史跡指定の「吉野ヶ里遺跡」がある「吉野ヶ里歴史公園」です。弥生時代の建物が98棟復元され、当時の暮らしが人形で再現されています。
歴史スポットはまだあります。明治日本の産業革命の世界遺産「三重津海軍所跡」です。この遺跡は、木の風化を防ぐために地中に埋まっており、「見えない世界遺産」として知られています。資料や、バーチャルスコープで見えない遺産を見ることが出来ます。
また、佐賀県のパワースポットとして人気なのが「祐徳稲荷神社」です。日本三大稲荷の1つでもあり、年間約300万人の人が訪れています。敷地には、祐徳博物館が隣接しており、貴重な歴史の品の数々を見ることもできます。
そして佐賀県といったら忘れてはいけないのは、「佐賀城本丸歴史館」です。佐賀城跡に佐賀城の本丸御殿を復元した歴史館になっています。木造の復元建物としては日本で最大級になります。佐賀の歴史を知るうえでは是非見たいスポットです。
そもそも道の駅ってなに?
「道の駅」というのはどのような役割の施設のことを指しているのかご存じでしょうか。高速道路にあるサービスエリアは休憩所としての役割がありますが、一般道路にある「道の駅」には休憩所以外にも役割を持っています。以下で詳しくご紹介します。
道の駅は3つの機能を併せ持つ道路施設
「道の駅」は一般道路でも夜間に休憩できる場所が欲しいという声と、地域を活性化させる場所が欲しいという声を実現するために作られた施設で、国土交通省によって登録された施設のことを「道の駅」とよびます。
「道の駅」として登録するためには、3つの機能を備えていることが条件になります。3つの機能に関しては、以下で詳しくご紹介します。
「休憩機能」
「道の駅」を登録するために必要な3つの機能のうちの1つが「休憩機能」です。「休憩機能」とは、駐車場・トイレが無料で24時間利用できる施設であるということです。
「情報提供機能」
「道の駅」を登録するために必要な3つの機能のうちのもう1つは「情報提供機能」です。道路情報だけでなく、地域の観光情報や緊急医療情報などを提供している施設でなければなりません。
「地域連携機能」
「道の駅」を登録するために必要な3つの機能のうちの最後の1つは「地域連携機能」です。文化共用施設であったり、観光レクリエーション施設などの地域振興の施設であるかどうかも「道の駅」には必要な要素となります。
全国の道の駅の数は1160箇所
「道の駅」は、1993年に103箇所が登録されたことからはじまり、今では北海道から沖縄まで全国で1160箇所(2019年6月現在)もあります。
![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)