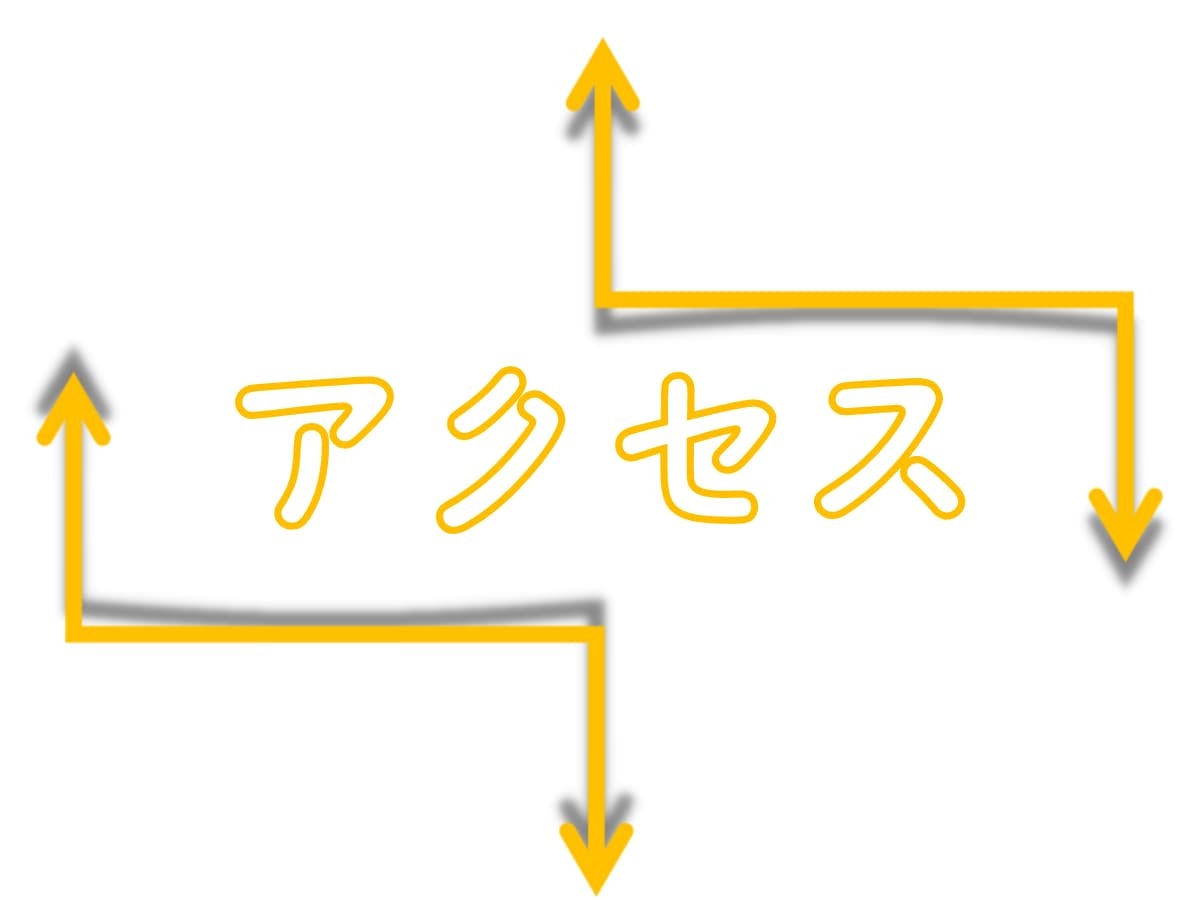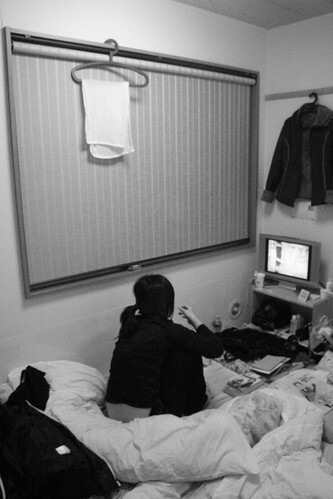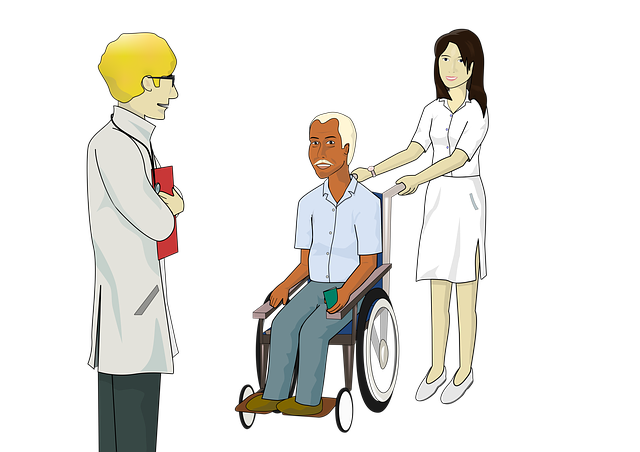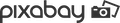本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。
東京の「山谷」は時代とともに変化してきた町!
「山谷」という地名を聞いて何を思い浮かべるでしょうか?「山谷」ほど年代によって思い浮かべるイメージが変わる町も珍しいかもしれません。
それは「山谷」という町が時代とともに変化し続けてきた町だからです。昭和から平成にかけては肉体労働者の町、いわゆるドヤ街として知られていました。あしたのジョーの世界といえばわかりやすいかもしれません。
近年は、肉体労働者が減り、観光目的の外国人が集まる観光客の町としての顔も持ち始めています。今回はそんな山谷地区の実情を、町の歴史や楽しみ方、抱えている問題などとあわせてご紹介したいと思います。
東京の「山谷地区」とはどんな所?
実は現在、「山谷」という住所は存在しません。正式な地名としては昭和41年を最後に消滅していて、現在は東京都台東区の清川、日本堤、橋場と荒川区南千住のあたりを指す慣習的な地名となっています。
素泊まり専門の簡易宿泊施設や居酒屋が立ち並び、かつては日雇いの肉体労働者が多く暮らすある活気のある町でしたが、最近は高齢化により日雇い労働者が減り、生活保護受給者や路上生活者が増えてかつてほどの活気はありません。
そのかわりに安価に宿泊できることや、都内への観光スポットへのアクセスも悪くないことから、外国人観光客の姿も目立ちます。
山谷の歴史
ここでは、山谷の歴史についてご紹介したいと思います。山谷地区の歴史は他の地域のドヤ街と比較しても古く、山谷という町の起源を辿っていくと江戸時代の中頃まで遡ります。
ちなみに山谷という地名の由来は、当時は三軒の家屋しかなかったので三屋と呼ばれとも、浅草の原、浅茅が原に続く三つ目の野原だから三野と呼ばれたとも言われていて、歴史書など文献によって諸説あり定説はないようです。
当時の山谷は遊郭が立ち並ぶ吉原や小塚原刑場に隣接していたため、遊女や革職人、処刑人などの身分の低い人々や、他の地方からやってきた流民たちが多く住んでいた歴史があります。
そうした状態は明治以降も変わらず、上京してきた人の中でも貧しい人々の受け皿となっていたようです。
労働者の街としての形が確立されたのは大正時代、関東大震災以後のことで、被災者の宿泊所がつくられ、そこに復興の為の求人が集まったことがドヤ街としての山谷の歴史の始まりであると言われています。
戦後も戦災に遭い困窮した人々の逃げ場としての役割が与えられ、求職者や職業を仲介する業者が集まり、宿泊施設なども整い、昭和30年代の高度経済成長の時代には日本屈指の労働者の町、ドヤ街となっていきました。
そして、現在は高齢化や求人の減少などにより、日雇い労働者の町としての歴史に幕をおろし、福祉と旅人の町へとしての歴史を刻み始めつつあります。
東京の山谷と比較!大阪の「あいりん地区」とは?
東京山谷地区の他にドヤ街、日雇い労働者の町として有名なのは、大阪西成の「あいりん地区」でしょう。あいりん地区は山谷地区との共通点も多く、成り立ちの歴史や周辺の環境、ドヤ街特有の文化などよく似た部分も多い町ではありますが違いもあります。
東京の山谷地区よりも、大阪のあいりん地区の方が高齢化が進んでいるため、一足先に労働者の町から福祉の町へと変貌をとげつつあります。山谷地区にも高齢化の波は迫っていますので、あいりん地区は山谷地区の近い将来の姿と言えるかもしれません。
また、あいりん地区には中国資本の居酒屋が進出するなど、少しずつ町の雰囲気が変わってきていますが、山谷地区は比較的ゆるやかな変化に留まっているなど細かい相違点があります。
東京・山谷へのアクセス
山谷地区へのアクセス方法をご紹介します。最寄りの鉄道駅はJRなどの南千住駅やつくばエキスプレスの浅草駅、地下鉄日比谷線の三ノ輪駅などです。
いずれの駅からも東京、渋谷方面へのアクセスは良好ですが、駅から山谷地区の中心地までは徒歩7分から10分程度ですので、観光目的であれば問題ありませんが、毎日行き来する生活の足としてはやや不便かもしれません。
普段使う生活足としては山谷地区の各所(清川二丁目、日本堤など)に停留所のある都営バスや台東区のコミュニティバスの方が便利かもしれません。
東京の「山谷」は日雇い労働者の町
先ほどからご紹介している通り、東京山谷地区は日雇い労働者や日雇い労働者を引退した人々が多数住む町です。したがって、普通の町とは様子がかなり違います。
アパートやマンション、戸建住宅などは少なく、かわりに簡易宿泊施設が立ち並んでいます。宿泊費は2000円台~3000円台が相場で、中には2000円を切る宿もあります。他の町ではあまりみかけない二畳や三畳一間の宿がたくさんあるのが特徴です。
また、労働者の憩いの場として居酒屋なども多いですが、チェーン店などはほとんどなく、個人経営の店が多いです。居酒屋に限らず、他の町でみかけるチェーン店はほとんどみかけません、例外はコンビニくらいです。
簡易宿泊施設を「ドヤ(宿)」と呼ぶ
山谷地区のような簡易宿泊施設が立ち並ぶ、日雇い労働者の町を「ドヤ街」と呼びますが、これは宿(やど)を逆さ言葉で「ドヤ」と呼んだことに由来します。
つまり、ドヤ街とは簡易宿泊施設(宿=ドヤ)が立ち並ぶ街という意味です。海外のスラムなどとの違いとしては、少数ではありますが日雇い労働者以外の中産階級の家庭が混在していることや、必ずしも重犯罪などが多発するわけではない点があげられます。
他の町とのボーダーも海外のスラムや貧民街などに比べると曖昧です。例えば山谷地区からはスカイツリーが近くとてもよく見えます。再開発されて、新しく華やかなスカイツリーや東京ソラマチ周辺とドヤ街である山谷地区の対比は、天国と地獄という言葉が良く似合います。
これは山谷地区に限ったことではなく、先ほどご紹介した大阪のあいりん地区とあべのハルカス、横浜のドヤ街である寿町とみなとみらいや元町、山手の高級住宅地というように、日本中でそうした対比を目にすることができます。
山谷地区へ出かけた際には、ぜひともこの対照的な光景を眺めてみて下さい。どのような考えを持つにしても、こうした光景が存在するということを知っておくことは、とても大切なことだと思います。
日雇い労働者が通う日中営業の「居酒屋」も多い
山谷やその周辺の町には日雇い労働者たちが足しげく通う居酒屋がたくさんあります。山谷の居酒屋の魅力はなんといっても昼間から、営業していることでしょう。
もちろん他の町の居酒屋のように、居酒屋ランチを提供するためではなく、昼間からお酒を提供するために営業しているので、つまみもお酒も注文し放題です。
昼間から、居酒屋で誰からも白い目で見られることなく、お酒を飲むというのは、お酒や飲み会好きの人であればドヤ街の住人でなくても一度はやってみたいことではないでしょうか?
昼から一杯ならぬ、昼から本気飲みを体験するために山谷の居酒屋にでかけてみてはいかがでしょうか?
城北労働・福祉センター
城北労働・福祉センターは山谷地区の日雇い労働者の生活相談や職業相談を行う公益財団法人です。主な業務は生活保護などの福祉相談、医療相談、住民登録や戸籍相談、住宅相談、衣食住などに関する応急援護相談と就労支援(職業紹介、労働相談)などです。
他にも娯楽室や敬老室なども提供しており、テレビの視聴、将棋や囲碁、読書などが楽しめます。また、敬老室では高齢者が抱える悩みなども相談することができます。
なお、相談や支援を受けられるのは、主に山谷地区の日雇い労働者で利用者カードが給付されている人に限定されていますので注意が必要です。
いろは会商店街
山谷の「いろは会商店街」をご紹介します。見た目はどこにでもある、少し歴史を感じさせる商店街ですが、やはり山谷の商店街というだけあって、日雇い労働者向けに特化されています。山谷地区で暮らす上で必要なもののほとんどがこの商店街で手に入ります。
取り扱われている商品は実用的で安価なものが多く、他の町ではあまり見かけない種類の商品が多いので、山谷ならではの雰囲気が味わえる場所の一つと言えます。
また、「あしたのジョー」の舞台の一つが山谷であったことから、「あしたのジョー」とのコラボも行われていて、町のそこかしこに「あしたのジョーの」イラストや像があります。
月極ロッカー
山谷の町では簡易宿泊施設や居酒屋と並んで、よく目にするものとして月極ロッカーがあります。日雇い労働者は簡易宿泊施設を利用しているか、路上生活をしている人が多いため、所持品をしまっておける場所が必要であるためです。
一月の利用料金は大きさにより3000円から5000円で、1日あたり100円から170円程度で利用できる計算です。観光で山谷に来る人にはあまり縁のない場所ではありますが、長期滞在するのであれば便利な施設かも知れません。
東京の山谷を象徴「山谷ブルース」「あしたのジョー」
山谷ブルースはフォーク歌手、岡林信康のデビュー曲です。山谷地区の日雇い労働者の悲哀を歌った内容で一世を風靡しました。
当時としても、かなりインパクトのある楽曲だったようで、後に吉幾三や八代亜紀、北原ミレイ、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドなど著名な歌手やバンドがカヴァーしています。
リリースされてから50年以上経ちますが、どこか現代にも通じる内容で古さを感じません、悲しく辛い内容ですが、心にしみる良い歌ですので1度聞いてみてください。
また、先ほど「いろは会商店街」をご紹介した際に簡単に触れましたが、山谷地区は「あしたのジョー」の舞台としても有名です。
「なみだ橋を逆に渡り~」のフレーズで有名な「泪橋」も実在する地名です。残念ながら残っているのは地名だけで、橋が架かっていた思川も暗渠(あんきょ)化され地下に埋まっているため、当時のおもかげを目にすることはできません。
とはいえ、山谷地区には「いろは会商店街」をはじめ「あしたのジョー」そして「山谷ブルース」が発表された当時の雰囲気を感じさせる場所が、まだまだ残っていますので、おもかげを探しながら散策してみるのもよいかもしれません。
東京の「山谷」が復活!様変わりした現在の治安は?
山谷地区はゆるやかにではありますが、確実に変化しています。労働者の需要の減少や高齢化などの影響により、年々日雇い労働者は減少していて、かわりに外国人観光客などの宿泊者が増えて来ています。現在は新型コロナウィルスの発生により、その状況は変わってしましましたが、以前は年末年始の宿泊客の100%が外国人観光客だったという宿泊施設もあるほどでした。
また、高齢化によって以前の様な危険な雰囲気がなりを潜め、治安が悪さが改善するという皮肉な結果も、観光客が増えている要因のようです。治安が改善することはとても良い事なのですが、かつての活気も失われているのは寂しいことなのかもしれません。
山谷地区は今まさに変わり始めていますので、今が最後、今しか見れない、そんな光景がたくさんありますので、興味を持った方は今、山谷を訪ねてみてください。
若い人がカフェ等をオープン!東京・山谷の再生
徐々に衰退していっている山谷地区ですが、山谷の再生を目指す動きも出て来ています。山谷地区に限らず、ドヤ街は地域の住民と日雇い労働者、路上生活者、そして近年増えている観光客によって構成されています。
これらの人々の交流や町の外から観光で来た人々に山谷の現状や文化、歴史を知ってもらうための場所として、2018年に「さんやカフェ」というカフェがオープンしました。※2023年1月14日現在、臨時休業中です。
このカフェでは「思いやりコーヒー」というコーヒーを買うことができない誰かのために一杯分の代金を前払いするという取り組みをしています。
相互理解と助け合いが進めば、山谷地区が新しく生まれ変われる日も来るかもしれません。
観光客(外国人含む)やバックパッカーの増加
これまで記事内でもたびたび触れていますが、新型コロナウィルスが発生するまでは、山谷地区を訪れる観光客が増加しています。特に山谷地区に宿泊する外国人観光客は2002年のFIFAワールドカップの頃から、増加し続けており、最近は英語に対応する施設や外国人観光客向けの宿泊施設が新設されていました。
山谷スタディツアーも開催
また、最近は日本人の間でも山谷の歴史や文化、高齢化やそれに伴う福祉の問題に興味や関心を持つ人が増えています。そうは言っても単独で山谷地区を訪れるのは中々ハードルが高いので、二の足を踏んでしまう人も多いそうです。
そうした人々のニーズに応えるために、山谷地区で炊き出しや医療支援などのボランティア活動を続けてきたNPO法人山友会が、山谷スタディツアーを開催しています。山友会の活動内容に触れたり、実際に町を歩いたりして、山谷の現状を知ることができます。
無用なトラブルを避ける意味でも、最初はこうしたイベントに参加するところからはじめるのが、よいかもしれません。参加費用は1人税込み2000円で1回のツアーにつき10名程度が定員となっています。開催日時は山友会のホームページで告知されています。※2023年1月14日現在、新型コロナウィルスの感染状況が収束するまでは中止となっています。
現在の東京「山谷」の楽しみ方
山谷地区の最寄駅は南千住駅、浅草駅、三ノ輪駅となっていますが、距離の近さや道順の単純さから南千住駅を利用するのがおすすめです。
南千住駅から吉野通り南へ向かって7分ほど歩くと、明治通りとの交差点に到着します。ここがあしたのジョーなどで有名な泪橋の跡地であり、山谷の入り口です。ここから南側がいわゆる山谷地区となります。
さらに吉野通りを南下して、日本堤交番の手前の道を右折すると、先ほどご紹介した「いろは会商店街」のメインストリートに入っていけます。
「いろは会商店街」には2017年まではアーケードが設置されていてこれがシンボルのようになっていましたが、残念ながら現在は撤去されています。ですが、現在でも山谷特有の雰囲気を味わうことはできますので、ぜひ足を運んでみて下さい。
居酒屋や生活必需品を扱う店などが立ち並ぶ商店街を歩いていると、向かって左側、建物の切れ間や路地の先にスカイツリーの姿が望めます。昭和の雰囲気が残るドヤ街とスカイツリーとの対比は必見ですので、ぜひ足を止めて眺めてみて下さい。
かつてのアーケード街を道なりに進んでいくと土手通りにぶつかります。あしたのジョーの像はこの場所にありますので、あしたのジョーファンの方はぜひここまで歩きましょう。
また、一通り散歩が終わった後に一杯飲みたくなったら、「いろは会商店街」の土手通り寄り、あしたのジョーの像からもほど近くにある居酒屋「山谷酒場」がおすすめです。こちらのお店は2018年にオープンした比較的新しいお店です。
山谷の歴史や文化、雰囲気を知って貰うために、安心して飲める大衆酒場を作りたい。という考えで開店したお店ですので、山谷に言ったら是非訪ねたいお店です。この居酒屋でしか飲めない10種のスパイスを漬け込んだ焼酎「山谷酒」やおいしい料理が魅力です。
最後に宿泊先ですが、山谷地区の雰囲気をディープに味わうのであれば、「いろは会商店街」や路地を入った先に立ち並んでいる簡易宿泊施設に泊まるのも良いですが、山谷を初めて訪れのであれば、大通り沿いにある新しい観光客向けのホテルに泊まった方がよいかもしれません。
治安がよくなったとは言っても、他の町とは違う不文律やマナーもあるようですので、事前に情報を仕入れたり、詳しい人に相談したりするなど、住民の方の生活を徒に乱したり、逆にトラブルに巻き込まれないよう、十分に注意して観光を楽しんでください。
現在の東京「山谷」の問題とは?
最後に、現在東京の山谷地区が抱える問題についても触れておきたいと思います。現在山谷では日雇い労働者の高齢化とそれに伴う貧困化が進み、生活保護受給者や路上生活者が増え続けています。
ドヤ街の簡易宿泊施設で暮らす人の中で生活保護を受給する人は全体の8割とも9割とも言われていますし、様々な事情で生活保護を拒否したり、生活保護を受けられなかった、路上生活者も少なくありません。
また、オリンピック等で人手不足が叫ばれていたこともありますが、増えているのは若者の求人で、山谷に多く暮らす中高年向けの求人はむしろ減り、職業紹介の場である寄せ場も機能不全に陥りつつあるそうで、まだ働ける人も貧困から抜け出すのが難しくなっています。
城北労働・福祉センターなどの公的な団体や各種NPO法人などが、生活、医療、職業相談など様々な支援を行ってはいますが、全ての困窮者に充分な支援が行われているとは言い難いのが現状です。
こうした山谷地区の現状は日本の縮図であり、程度の差こそあれ全国各地に存在する問題です。また、高齢化と肉体労働の減少は既定の路線である以上、放っておけば状況は悪くなる一方で良くなることはありません。
そうは言っても、公的な支援にも限界はありますし、こうした貧困問題は自業自得であり自己責任であるという厳しい意見もあり、社会福祉の危機的な状況もあり、そうした意見が一定の説得力を持ってしまっているのも事実です。
また、2019年10月に発生し関東や中部、東北に甚大な被害をもたらした台風19号が上陸した際に、路上生活者2名が自主避難所への受け入れを希望したものの、住所がないことを理由に台東区の担当者に拒否されるという事態が発生して物議を醸したのも記憶に新しいです。
この問題については様々な意見や考え方もあり、未だに決着もついていませんので、ここでこれ以上取り上げることは避けますが、路上生活者が多く暮らす山谷地区のきれいごとでは済まない負の面を象徴する出来事なのではないかと思います。
これを機会に一人一人が社会福祉について考え、自分に何ができるのかを真剣に考えなければならない時が来ているのかもしれません。
時代とともに激動した東京の「山谷」地区を知ろう!
ここまで山谷地区の歴史や現状、楽しみ方をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?この記事が、江戸時代にはじまり明治大正昭和の激動の時代に東京を支え、そして平成から令和へと今まさに歴史的な変化の時を迎えている山谷地区を知る一助となれば幸いです。※本記事中の情報は2023年1月14日時点のものです。
![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)