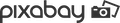本サービス内ではアフィリエイト広告を利用しています
店舗や施設の営業状況やサービス内容が変更となっている場合がありますので、各店舗・施設の最新の公式情報をご確認ください。
福島の大内宿は半農半宿の宿場町
福島県南会津の人気観光スポット・大内宿(おおうちじゅく)は、会津若松と日光今市(いまいち)を結ぶ重要な道の宿場町として栄え、江戸時代には多くの旅人が立ち寄りました。
会津藩や庄内藩、米沢藩などの参勤交代や江戸廻米(かいまい)の運搬路として重要な役割を果たしていた大内宿は、脇住環(わきおうかん)の通行取り締まりによって途絶えていきます。
脇住環とは、脇街道や脇道ともいい、江戸時代の五街道(中山道・日光街道・奥州街道・甲州街道)以外の道をいいます。街道には、通行を制限するための関所が置かれました。
賑わいを失った大内宿は商人や旅人だけの宿場となり、大内宿の人々の生活は「半農半宿」へと変わっていきます。
大内宿の人々は、宿場として旅人の休息のための便宜を図ったり、人馬の継ぎ送りから得る荷駄賃で生計を立てるかたわら、大豆や小麦などを農業生産していました。宿駅と農村の二つの顔を併せ持つ大内宿は、半農半宿の時代が続いたのです。
福島・大内宿の歴史
江戸時代、会津藩初代藩主・保科正之(ほしなまさゆき)によって、会津城下と下野(しもつけ)の国を結ぶ約130kmの街道が整備されました。大内宿は、別名下野街道、南山通りとも呼ばれた会津西街道の宿場として栄えました。
1643年(寛永20年)頃には、若松と江戸を結ぶ街道に現在の町並みが形作られたといわれています。大内宿は、参勤交代や江戸廻米の輸送などに利用された重要路線でした。
参勤交代は、各藩の大名が一定期間に交替で参勤した江戸時代の制度です。参勤とは国元から江戸に赴く旅、交替は江戸から国元へ帰還する旅のことをいいます。江戸には正室と世継ぎが常駐しなければならず、諸大名は一年ごとに国元と江戸を行き来していました。
参勤交代は将軍と大名との主従関係を示す軍事儀礼ではありましたが、政治的な統制だけではなく、江戸と国元の文化、経済の交流にも大きな役割を果たしたといわれています。
大内宿を通っていた脇街道での参勤交代はその後禁止され、1680年(延宝8年)には白河城下町を経由する白河街道へと移行、大内宿の人々は半農半宿の生活となります。
![jouer[ジュエ] jouer[ジュエ]](https://cdn.jouer-style.jp/images/production/sites/logos/000/000/001/original.png?1592368978)